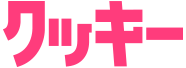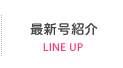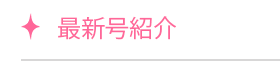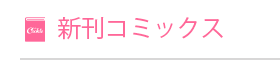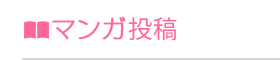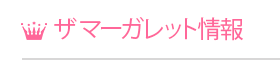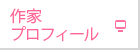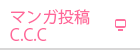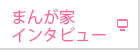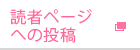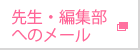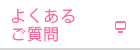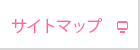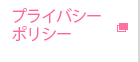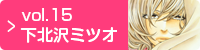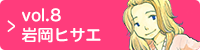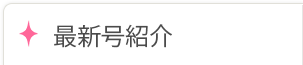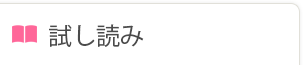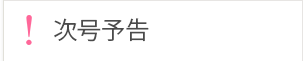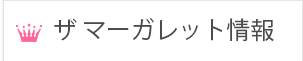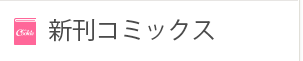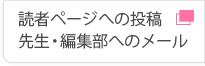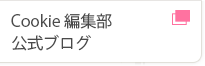本誌「C.C.C.」内で、様々な作家さんにキャラクター論について語っていただくコーナーが「キャラクター作りの神髄」!
HPでは、その取材模様の全文を公表します!
Vol.01:高須賀由枝先生
自分自身が好きなキャラの組み合わせで描く
- 編集ケンケン(以下、K) 「グッドモーニング・コール」、「グッドモーニング・キス」とずっと同じキャラを描き続けることって、すごいことだと思います。
菜緒や上原くんたちはどのように生まれたのでしょうか? - 高須賀由枝先生(以下、高) 初めは、同居モノにしようっていう発想は無かったんです。
私自身、王道なヒーローが好きだったので、クールで硬派で、実は優しい、王道な王子様キャラとして上原くんが出来ました。 - 高須賀さん自身は、上原くんみたいな人がタイプだったりするのでしょうか?
- いえ。実際の男性の好みではなく、マンガとして、王道が好きで、キャラも展開も王道が何でも好きなんです。
「王子様と普通の女の子」って王道な組み合わせじゃないですか。
なので、菜緒も普通な女の子にしようと思って作りました。
特殊な何かがあるとか、人気者とかではなく、普通の女の子に。 - なるほど。特に何か事情や悩みを抱えているとか、特殊な存在ではなく、フラットで入りやすい子ですよね。
- ただ、普通の女の子と王子様な男の子って、接点がないですよね。
上原くんは、硬派な男の子だから、女友達もいないだろうし…。
となると、2人が仲良くなるためには、一緒に住むくらいしないとだな〜と。 - そこで同居という設定が出てきたのですね。
- 親しくなるためのキッカケくらいにしか思ってなかったですね。同居設定は。
同居させたからといって、菜緒もすぐに上原くんを好きになるわけではないし、どうやったら好きになっていくかを考えて作っていきました。
マンガは自分の長所を伸ばした方がいい
- 「グッドモーニング・コール」とそれ以前の作品との違いはありますか?
- 今までの私のマンガ作りって、引きや展開をメインに作ってたんです。
毎回、何か派手な事件を起こしたり、ベタフラッシュで終わるような引きを!
それをやると当然、キャラの心情に無理が出てきますよね。
たとえば主人公の女の子を2人の男が取り合って「勝負だ!」とか、そういうのを描かなければいけないのかな…って(笑)
マンガってそういうものなんだよな…と思い込んでて。 - ああ〜。展開主導で描いていたわけですね。
- だけど、当時の担当さんが「無理して描いても面白くならないし、そういうのは向いてない。
あなたはキャラのちょっとした言動が面白いよ」って言ってくれて。
「グッドモーニング・コール」からは、キャラのちょっとした掛け合いを前に出したり日常をしっかり描くという作風になりました。
なので「グッド」からは、私の作風は無理せず、ゆる〜くなってます(笑)。 - 無理をせず、本来の高須賀さんの持ち味を大事にしたわけですね。
- はい。なので、同居設定だけれども、同居モノでよくありそうなエッチな展開とかは私はうまく描けないなと思ったのでやりませんでした。
得意なものを伸ばした方が良いと思うんです。 - 自分の武器にあったものを描くというのは、非常に大事なことですね。
それは作風でもキャラの感情でも、絵柄でも。それを武器にできるマンガを描くというか。 - そうですね。重い展開とかも私は描こうと思ってもうまくいかないので、描かないでおこうと思って、やりません(笑)
キャラの感情の流れは作者も分かっていること
- キャラを作るときに意識していることってありますか?
自分をマンガのキャラにしたらどんな子になるか、で描いているとか。 - 自分を投影するわけでもないし…すごく頭が良い子とか、運動が出来るとか、すごく馬鹿な子とか、設定から作ってはいません。
私の描くキャラって、みんな普通だと思います。 - みんな…普通?
- 普通の感覚を持っているというか、感情の流れが理解できる、みんなが理解できる感覚を持っているキャラたち=普通のキャラでしょうか。
作者自身がそれぞれのキャラの感情の流れが腑に落ちるように描いています。 - なるほど。そういう「感覚」という意味での「普通」ですね。
感情の流れが理解できないと読者は「あれ!?」って止まってしまいますからね。 - はい。感情の流れの「普通」を大事にすることがキャラ作りでは大事だと思います。
だけど、菜緒も上原くんも、まりなもみんな普通で、それぞれ性格が違います。
生まれつき備わっている顔の良さとか、身体的な差はありますが、みんな普通の子。 - 確かに…! 突拍子もない性格とか、変わった設定とかはないですが、
それぞれの性格がちゃんとありますし、それが読者に伝わってますね。 - それぞれ違うのですが、どの感情の変化も自分でちゃんと理解して描くことですね。
- キャラクターで一番大事なのは、感情の部分だと思うので、
その場その場の菜緒や上原くんの心情をしっかり読者が掴めることは、何にも勝って大事だと思います。
では、キャラの性格付けは、キャラ表などを作って行うのでしょうか? - 私はキャラ表も作らないし、カッチリとしたプロットも作らないんですよ。
- ええ!? プロットも作らない?
- 結局、かっちりプロットを作ったとしても、その通りにネームを描くと、こなしているだけになっちゃうんです。
描いていて、面白くないので、結局ネームにするときに、また頑張らないといけない。
そういう意味でプロットは重視していないです。
- おお…納得です。あらすじをなぞっていても面白くならないです。
ではキャラ表を作らないで、どうやってキャラを作っているんですか? - その場その場でやっています。ネームを描くとき、淡々とあらすじをなぞってても面白くないので、アクセントが欲しいなと思う。
そういう時がキャラの出てくるところ。 - ネームを描いて、面白くないな…と思った時に、キャラクターを立たせることで面白さを入れていくということですか?
- たとえば菜緒は最初はここまで天然な子ってつもりじゃなかったんです。
ネームを描いていて、何か悩むポイントがあったときに、悩ませて描いてみたら「何か違うな…」「しんどいな」ってなったんです。
なので、悩ませずに「まいっか。何とかなるなる!」っていう風に動かしてみたら、その方が気持ちよかった。
周りの友達が「え〜大丈夫!?」ってピンチだと言ってくるのに菜緒は能天気で悩まない。
その方が面白かったので、そういう子になりました。 - おお…! まさにネームは面白くなったもの勝ち、ライブ感がありますね。
先にキャラ表から作っていたら、キャラ表通りの型にはまった行動しかせず、面白くキャラを動かす障害になってしまうかもしれません。 - 周りが「え、それ大丈夫?」って言うことでも、菜緒は悩まないという行動パターンが出来てからは、それを繰り返していけばいいんです。
悩みそうな時は「ま、いっか」っていう。
それをやると、今度は菜緒が「ま、いっか」で済まさない時、アクセントが出来る。
キャラがあると良いことづくしなんです。 - キャラの行動パターンというか、行動原理が分かると、読者も「この子、こういう子なんだな」と伝わりますからね。
- そうです。キャラが立っているってことは、そのキャラがどう動くか、どんなことを言うかが、マンガに描かれてなくても想像がつく、
それが、キャラが立っているってことだと思います。
キャラって何かといえば1人の人間ですし。 - マンガに描かれていなくても、その前後のイメージが膨らむマンガってすごく人間が描けていると思います。
高須賀先生流のキャラクターの掴み方
上原くんはどうでもいいケンカなんかしない
- ちなみに上原くんのキャラを掴んだキッカケは何ですか?
- 菜緒と上原くんにケンカをさせようと思ったんですよね。
ケンカして仲直りしたら、2人の距離が近づくじゃないですか。
それをやりたかったんですけど、上原くんは菜緒のどうでもいいケンカなんて買わないキャラなので、
どうしてもそういう風にネームが描けなかったんです。 - おお…! 「このキャラはこんなことしない!」というやつですね。
- その当時は、まだ展開を盛り上げることが大事だと思っていたので、ケンカさせて仲直りって、盛り上がるじゃん!と思っていて、
そうさせたかったのですが、出来なくて…。
それを担当さんに言ったら「無理にケンカさせなくて良いんじゃない?」って。
それじゃあ盛り上がらないですよ!って言ったら「無理して盛り上げなくても面白いよ」って言うのでハッとしました。
そっか。キャラに無理させようとしてた…!って。
でも、それで描いてみたらすごく腑に落ちて、キャラを大事に描こうって思いました。 - 展開よりもキャラ重視で良いんだと思ったわけですね。
- その方が無理がなくて良いと思うんです。
展開のインパクトやショッキングさ重視だとインフレしていきますし。
他にも、伏線とか張りたくなるじゃないですか。
でも、伏線張ってもバレるようにしか描けなかったので、そういうのも無理してやらない方が良いんだなと。
展開も「続きはどうなるんですか!?予想つきません」って言われた方がいいですよね。
先々の展開を作者も分からないで描くんです。そうすれば読者も分からないから。
それでいいんだと思うようにしました。そうしないと描きつづけられないですし。 - 先々の展開をガッチリ固めて、伏線を張っても、先が読めたり、伏線がバレてたら苦労がもったいないですからね。
それよりかは、その時その時のキャラの感情の流れに乗れることの方が大事に思います。 - キャラクターっていうと、外側の設定とかを重視している人がいますけど、本来キャラって内面から作るものだと思います。
キャラが最も表れるのは感情の流れですから。 - 設定とかは替えが利く外側の部分ですからね…。
「帰国子女で日本文化に疎くて、いつも見当違いなことをしてしまう子」とかは、「帰国子女」の部分を「超ド田舎で生まれ育って」とかに替えることもできますし、誰だって描くことができる設定。それだけではキャラは掴めませんね。
差が出るのはキャラクターが抱く感情をどう切り取って描くかの部分ですね。 - そういう意味で言えば、プロットも外側部分ですよね。
内側の感情とはまた別の部分。プロットは単なるあらすじ、段取りなので。
自分が感じたことのある感情から描く
- どうやったらキャラの内面を上手く描けるでしょうか?
- やっぱりキャラの感情を分かっていることなので、自分が日々思っていること、感じたことをそのまま描けば良いと思います。
現実に起きているものをマンガに繋げて描けば良いかなと。
たとえば、バイト先に自分のことを好きな男の子がしょっちゅう来て、「あ〜面倒だな〜」という気持ちとかでも良い(笑)。 - そういう身近な気持ちの方がリアルで共感なりしやすいですね。
- 案外、新人さんや投稿者さんって、自分の周りで起こっていることは普通過ぎてネタにならないと思いがちなんでしょうけど、私はゼロからは作れないし、自分の感じたものしか描けないので、そういう描き方でやってます。
- でも、だからこそ、それぞれのキャラの感情をちゃんと作者が理解していて、読者もキャラに感情移入できるわけですよね。
- Kissで描いている『コミンカビヨリ』も、その時の私のテーマが「老後が不安!」だったので、描けたお話です。
- 将来が不安なフリーランスの女の子が古民家を買うのが出だしでしたね。
- あれは、ちょっと前の私そのものの気持ちでしたね!
色々老後のお金のこととか調べてたんですよ(笑)。 - まさに高須賀さん自身の感情がキャラに…! 一部の感情をフューチャーして、そこにスポットを当てて描くから実感がこもるわけですね。
キャラを単なる記号からどう肉付けするか
- あと、最近の『コミンカ』のネームで言えば、主人公のライバルの女の子キャラを出そうと思ったのですが、
人物像が固まらないと描けないんですよね。
最初は、「ワガママな都会的な子」っていう記号みたいなキャラだったんです。
そこから、どういうことをしゃべるかなと考えていきました。
展開的に主人公にライバル宣言をさせることは決まっていたので、どういう言い方で言わせるか…どんなシチュエーションで言わせたらキャラが立つかということを考えていきました。 - やっぱり、あらすじが決まっていたとしても、どういう感情で描くかがポイントなのですね。
あとはキャラを立たせるというエンターテインメント的な視点も大事だと。 - そうです。なので、そのライバルキャラが、どういう風に知り合って、今までヒーロー役と友達だったのか、恋人未満だったのかとか、良い感じだったのか、そういう関係性によっても全然違うので、過去を固めて、どういう感情を作っていくかを考えていきました。
- ひええ〜。やっぱり脇役1人を取っても、そのくらい色々考えているわけですね。
- コマに表現しない、見えていないところまで考えないと感情は描けないと思うんです。
- 非常に勉強になりました。新人・投稿者へのアドバイスに役立てるよう頑張ります。今回はありがとうございました!